「 病院食とケンタッキー 」
1ヶ月ほど前、わたしは椎間板ヘルニアの精密検査で3日間入院したが、整形外科の入院なんて痛みさえ我慢できれば屁みたいなものだと思った。もちろん重症の人もいるし事故がらみだと重体の人もいる。不治の骨の病で死に至るケースももちろんあるだろう。だから誤解されては困るが、あくまで“ある一定期間治療をすれば治る”という前提の入院に関してだ。
「退屈」が最大の敵でテレビも本もすぐに飽きてしまった。それは回りの患者たちも同じらしく、結局は同室の6人と1日のほとんどを談笑して過ごすことになる。それぞれが体の1部に猛烈な痛みを抱えているが、それをなんとかやり過ごすためにも馬鹿話が必要なのだった。たいがいはそこの病院の悪口と他院の風評、時々おのれの痛さ自慢、まれに女の話、下半身の話などが出てきて真面目に人生相談が始まったりするから実に笑える。
わたしより数倍ひどい椎間板ヘルニアの藤井君の悩みは“彼女としてあげられない”ことで、“彼女が他の男とできてしまうのじゃないか”というものだった。慰めようもないので全員で「男女の仲はSEXがすべてだからあきらめろ」と言い放った。藤井君は夕方こそこそと電話をかけたりしていた。
わいのわいのとやっていると看護婦が「この部屋は娯楽室みたいねえ」と言って、ドアを閉めて出ていった。笑い声がうるさいらしいのだった。実はわたしたちの病室がいちばん霊安室に近いらしいのだった。
整形外科では特に食事制限もないし入院食も味付けが普通でまあ旨い方だ。酒以外ならほとんどなんでも持ち込みOKである。但し、動けないのに食い過ぎると太るのでみんな自粛しているようではあった。
さて、整形外科病棟と対極にあるのが内科の入院病棟である。雰囲気が実に陰鬱なのだ。陰鬱は伝染する。わたしは約15年前大腸癌の手術を受けたが、自分が死ぬかも知れないという状況は分かっていながらも、ほとんど開き直って瓢々としていた。陰々滅々としてみても命が助かる訳ではない。妻子のこと、金のこと、仕事のこと、と考えなければいけないことは山ほどあったが、考えることからは何も生まれないような気がした。とにかくメゲないように気分を陽に保ち、自分自身の免疫力を高めることで1日でも早く完治したいと考えた訳である。しかしだ……。
「明日手術です。小林さんみたいに馬鹿ばっかり言ってる人が隣にいてくれてよかったです。お互い退院して元気になったら、どこか外で寿司でも食いたいですね」と言っていたのに、2度と病室に帰ってこなかった人が2人いた。わたしはその度に、自分がいかにラッキーであったかを痛感した。手術は失敗に終わることがあるのをあらためて思い知らされた。
「色々お世話になりました、末期だったんです」と後日奥さんがあいさつに来た。奥さんの薄い皮膚を見ながら、わたしは頭の中で、彼が最後に言った“寿司”のことばかりを考えていた。無理なことは解っているが、手術前夜ぐらい食べたいものを食べさせてあげたかったなあ、とわたしは主のいないベッドの白いシーツを見つめた。
内科入院病棟の飯はまずい。もっとも“おもゆ”は飯と呼べるものではないし、飯を食いに来ているわけではないので文句も言えない。が、多少元気になって回復しかけの患者にとっては半ば拷問に近い。点滴を打っているので腹が空かないという理由もある(これは本当、何年かは点滴だけで生きられるのだ)が、塩分、糖分、脂肪分を大幅にひかえた食物は抜殻以外のなにものでもない。食事の時間はお通夜のようだった。
わたしは回復するにつれ部屋の名主みたいになってゆき、新規入院者や年寄りの世話をした。とにかく早く退院したかったのでリハビリのつもりで動き回った。30Cmぐらい開いた腹の傷は、動きすぎるとまだ血がにじんだりしたが不思議とあまり痛みを感じなかった。元オートレースの選手で八百長で資格剥奪された増田という男と、肺癌のくせに夕方になると必ず病院を脱走してワンカップを飲んで帰ってくる塚田というジジイと3人で、同室の人たちの世話を焼いた。婦長にはいつも「部屋が明るくなっていいんだけど、うるさい、うるさい」と怒られていたが、今思うとただの「ウザイ3人組」であった。
あと1週間ぐらいで退院というある日、わたしより10歳は若い田島君という青年が晴れて退院することになった。胃を3分の2切除したが完治しての退院だ。大部屋牢名主としてもこんな嬉しいことはない。
「小林さんには世話になりました。なにかお礼をしたいんです。食いたいものないですか。もう何食っても大丈夫でしょ? 栄養もつけた方がいいし」
わたしは単純に遠慮し「気を遣うなよ」と言った、が頭の中ではすでにメニューを開いていた。人生と書いて矛盾と読むとはよく言ったものだ。もうすぐ退院だという段階になって謎の腹痛なんぞを起こしてしまったら、心配をかけた親や妻子や友人たちに会わす顔が無いなあ、と思いつつもわたしは誘惑に勝てなかった。
「ケンタッキー・フライドチキンを腹いっぱい食いたいなあ、今は」
田島君は20分後にファミリーパック(?10個入りのやつ)を2パック持って現れ、ガハハハと笑って風のように去った。わたしはあっけに取られたがすぐにそれを戸棚に隠した。が、ご存じの通りものすごい香りである。バレたら没収に間違いない。しかしどうあっても温たかい内に食いたいではないか、わたしは窓を開け放って風を通し、看護婦の目を盗んで各人へ2個ずつ配給した。そしてベッドの上で新聞を広げ、その陰で“飢えた原始人のような顔”で頬ばった。
おそらく、それはわたしの一生の中でもっとも美味でジューシーでとろけそうで、生きていて良かった〜と思った瞬間だった。唇にからみつく油脂、口の中で溶ける皮、程よい塩分と酸味を帯びた肉、歯ごたえと旨味を合わせ持った軟骨、男女の禁を犯す快感にも似た髄液の味、わたしは城拓也の「骨まで愛して」を口ずさみながらむさぼり食った。
神経質な十二指腸潰瘍の患者も、クレバーなはずの胃癌患者も、点滴で満腹の肺癌患者も禁を破ってケンタッキーを口にした。食は快楽である。食は至福への誘いである。そして食は「生」そのものなのだ。わたしの目からは涙が流れた。
(まったくの余談だが、今まさにビルの屋上から飛び下り自殺をしようとしている人に飯を食わすと、たいがいは自殺を思いとどまるそうですな。「テレビのちから」に対抗して「飯のちから」というアイデアをプレゼンしてみようか)
禁断の肉を食らった夜、幸いにも腹痛などを起こす者は出なかった。婦長に説教をされながらわたしはホッと胸を撫でおろした。が、その後わたしが退院するまでの1週間の間にハイケア(集中治療室)に連れていかれて2度と戻って来ない人が又1人出た。チョットだけ気にはなっているのだが、わたしは……ケッタッキー・フライドチキンのせいだった、とはなるべく(?)思わないようにしている。
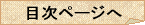
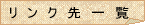
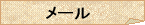 ・
・