「 読唇術 」
子供の頃に観た映画、確かそれは時代劇でしかも忍者物だったような気がするが、その映画の中で水団(すいとん)の術や葉隠れの術といっしょに「読唇術」なるものが出てきたのだった。他人の唇の動きを見て何を言っているのかを理解するというその術に、わたしは以来ずっと憧れを抱いていたのだが40歳を超えた頃のある日、なぜか知らぬ間に自分にその術が備わっていることに気がついたのだ。
「ウッソ〜! 大ボラ吹き〜! 詐欺師〜!」とか言わないで、まあ聞いて。
もちろん長〜い会話を100%分かる訳でもないし、ちょっとおおげさに言い過ぎかもしれないが、ボイストレーナーとして10年近く他人の口元を見つめて文句ばかりを言ってきたせいかも知れなかった。皆さんだって「こんにちわ」「さようなら」「いやだ〜バカ!」「ウッソ〜! ゲ〜ッ!」ぐらいはわかるでしょう? まあそれの3倍ぐらいの程度だと思って頂ければ分かりやすいと思う。
「ダメダメ、今そんなことをしたらわたしたちが殺ったってバレてしまうわ」ぐらいの長さならなんとかわかる程度である。
ボイストレーニングというのは、ある意味とても退屈なもので来る日も来る日も「ア・エ・イ・ウ・エ・オ・ア・オ」とかやってる訳なのだ。で、いくら“プロ養成コース”の生徒でも飽きてくる。わたしはなんとか飽きさせないようにと工夫を重ねていたのだ。
日本人には本来16ビートの乗りというものが無いので、歩く時常に「タカツク、タカツク、タカツク、タカツク」と早口で言わせてそのリズムに合わせて歩かせたり、ロートにピンポン玉を乗せて吐く息で空中に浮かす装置を作り、生徒にピンポン玉の滞空時間を競わせたりした。そんな訳でわたしのレッスンは人気があったが、読唇術もわたしはレッスンの中にとり入れていた。
つまり、歌う人は声を出さず、それでも相手に歌詞がわかるような正しい口の動かし方をし、残りのクラスメイトは必至に歌い手の口の動きを見て歌詞を読み取るという集中力養成の時間を設けたのだ。まじめに取り組んでいる者は確実に発音が良くなった。わたしはなるべく楽しくレッスンを進めていくようにしていたが、根底の取り組む姿勢については厳しかった。読唇術は遊びのようにも見えたがちゃんと理にかなったものではあったのだ。クックッ、自慢、自慢。
「今はまずいわ! 祖国のために戦ってきた努力が全部無駄になるわ!」ぐらいの文章はみんな分かるようになった。
Aちゃんは非常に優秀なわたしの教え子だった。才能もあったし努力家でもあった。実際に色々なオーディションで賞を取り、“運”さえあればプロデビューできそうな実力だった。容姿・歌唱力・性格をそれぞれ10点満点とした総合点では28点はあげられそうだった。ちなみに27点がプロの最低ラインとわたしは考えていた。これはかなり厳しい採点でアイドル系歌手などは実際プロでやっていても27点以下のやつが多い。
そんなAちゃんがある日、レッスン途中にわたしの目の前で泣き崩れた。スタジオの中で歌っていて突然のことだったので、同じクラスの仲間もそしてわたしも訳がわからなくて阿気にとられたのだが、どうやら想像するところ、歌っていたのがかなり悲しい不倫系の歌で、感きわまったらしいのだった。
「先生! ……もう歌えません」
彼女はそう言ってスタジオを出て行った。なんとなく気まずい雰囲気になってしまったスタジオでわたしは他の生徒に事情徴収をこころみたが、誰一人くわしいことは知らないようだった。
「すみませんでした」
Aちゃんはトイレでひとしきり涙を流したあと、照れ臭そうに「ボリボリ」と口に出して言いながら頭をかいて戻ってきた。
「大丈夫か?」
「はい、大丈夫です」
「立ち直れるか?」
「大丈夫です、ごめんなさい」
わたしは「いいなあ若いってことは! 青春だあ〜!」などと森田健作の真似をして馬鹿を丸出しした。なんとか気分を明るくしてやろうと元気の出そうな歌まで歌って、アホもサービスした。
そんなことがあってAちゃんとわたしは急速に仲良くなり、レッスンのあと酒を飲んだりするようになった。もちろん1対1ではない、いつも2〜3人の生徒といっしょである。しかし帰りの電車は同じ方向で二人きりになるので、わたしは3ヶ月ほど経ったある日、余計なお世話だとは思いながら気になっていたことをストレートに聞いた。
「妻子のある人を好きなのか?」
Aちゃんは少し困ったような顔をしながら何も言わなかった。わたしには、妻子ある男性を好きになってボロボロにされ今や行方さえわからないといった別の女性の知人がいたので、単純にAちゃんのことを心配して尋ねたのだった。親心みたいなものである。Aちゃんは23歳、娘と言ってもおかしくはない。
「どうしたらいいかわからないんです、頭の中にその人の名前が150個ぐらいあって……」
Aちゃんは認めた。100個でも200個でもなくて150個というのが微妙だが、まあかなり思いつめているらしいのは雰囲気で分かった。わたしは少しキツイかな、と思いつつも“先生もしくは親としての助言”をした。不倫を否定するのじゃなくて、少なくともあと1年は音楽に没頭して欲しい……というような意味あいで助言したのだった。
「男になるんだな、今は。男になりなさい、男に」
Aちゃんは頭のいい女性だった、わたしの言葉の意味するところをすべて理解したように、微笑んで可愛くうなづいた。
「しばらく男になります、ありがとう先生」
乗り替え駅でわたしは電車を降り、ガラス越しにAちゃんを見送った。Aちゃんは「男になるよ、男になればいいんですね、男になってみせるよ、性転換、性転換!」と確かに言った。せ・い・て・ん・か・ん? と「目」を疑ったが、わたしは読唇術が使えるんだから一字一句間違いなかった。
その日、Aちゃんはいつもより少し飲み過ぎているようだった。万全の準備をして受けたレコード会社のオーディションに、あろうことか1次審査で落ちてしまったことが原因であるようだった。男になった筈のAちゃんが珍しく女々しく酔っていた。妻子ある男のことなどを思いだして、また泣き出したりしなきゃいいが、とわたしは気をもみながらずっと彼女を見ていた。彼女もややうつろな目で時折わたしを見た。
そしていつものように帰りの電車で二人きりになった。わたしは、すこし足元がこころもとないAちゃんの腕を取ったりしたが、それとて親心の範囲だ。
あきらかにいつものAちゃんではなくなっていた。わたしのことを“先生”ではなくて“こばやし〜”と呼んだ。すべてがテンパリつつあった。
いつものようにいつものホームの位置でわたしは電車を降りたが、その日に限って何かのトラブルなのか電車がすぐに動き出さない。発車のベルが鳴り終わった瞬間に止まってしまった時間の中で、わたしとAちゃんだけが動いているような錯覚に陥った。
ガラス越しに彼女はゆっくりとしゃべり出した。
「お・と・こ・に・は・な・れ・ま・せ・ん。わ・た・し・は・お・ん・な・で・す。わ・た・し・が・す・き・な・の・は・あ・な・た・で・す。こ・ん・な・ふ・う・に・な・っ・た・の・は・こ・ば・や・し・の・せ・い・で・す。わ・た・し・は・お・と・こ・に・な・ん・か・な・り・た・く・な・い」
Aちゃんは何度も繰り返して言っているようだった。まったくまばたきをしない大きな目は、唇とは別に「助けて!」と濡れながら叫んでいた。わたしはあまりにも突然のことであたふたし、読唇術でAちゃんの言っていることはすべてわかっていたが「え? え?」とわからない振りをするのが精一杯だった。
電車はやがて動き出し、Aちゃんをゆっくりと運んで行った。点になって消えてゆく電車のライトを見つめながら、わたしはホームに立ちつくしていた。
読唇術を学ぶ前に読心術を学ぶべきだったのだろうか、とひとり立ちつくしていた。そしてAちゃんの赤い唇の動きを茫然と思い出していた。
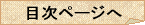
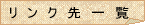
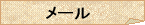 ・
・