「 注さん 」
新橋の飲み屋でサラリーマン4人組の会話を小耳にはさんだ。ザ・ドリフターズの「8時だよ、全員集合」のDVDを買おうかどうしようか……というような話だった。他人の会話に耳を傾けるなんてわたしも暇人に違いはないが、酔っぱらいにしては可愛い話題だったし、待ち人は来ないし、チビチビ飲みながらぼんやり退屈しのぎに聞いていた訳である。
わたしより10歳以上若い連中に見えたから「全員集合」が人気のピーク時にはおそらく小学生だっただろうと想像できた。いずれにしてもとりとめの無い、酒の肴話だ。誰が1番好きだったかというぐらいの話である。
「ドリフターズといえば長さんでしょう! なんたってリーダーなんだから」
「なに訳わかんないこと言ってんの! 結局誰が好きだったの? ドリフターズで一番面白いのはカトちゃんペッでしょ」
「味があるのは仲本工事だろよ、でもなんで“チャン名”がねえんだろな?」
「あれえええ? コーちゃんとか言われて……ないか!」
「高木ブーは今ウクレレで稼いでるな、知り合いがカルチャーセンターにいるけどブーのギャラって高いらしいなあ、別に好きじゃなかったけど」
「おれはエバちゃんが好きだったな、? ありゃあゴールデンハーフか?」
「馬〜鹿! 受け狙ってんじゃね〜よ〜、エバちゃんは好きだけどよ」
「志村の“ヘンなオジサン”はもういいな、改めて見るとなんか腹たつなあ、今の餓鬼はああいうのはもう嫌いだろ」
まったくもって言いたい放題である。しかし素人批評家には遠慮、利害、放送禁止用語がないので、正しい意見も多い、ような気がする。
しかしだ、ちょっと待ってくれよ、あの人はどこへ行ってしまったのだ? なんで誰からもあの人の名前が出てこないんだ?
「ドリフターズといえば荒井注だろうよ」とわたし個人は注さんに非常に思い入れが強い。彼の1発ギャグ「な〜んだ、馬鹿野郎」は実に爽快だった。子供たちが真似ると教育上よろしくないということで、PTAからクレームが付きそのフレーズを発する場面を減らされた、などという噂を聞くとなおさら好きになった。それと、わたしの叔父に顔が近い。ということはわたしにも似た部分があるということである。親近感は自ずと二乗になる。
中学3年時の担任・徳留先生は「小林よう、お前は頭も体も中途半端だから将来大物にはなれんだろう、小物にはなっちゃいかんし、そうだおまえは曲者になれ」と教育者としては大胆なことを平気な顔をして言った。口は悪いが情のある先生で、わたしは彼に「番長グループを1人ずつ闇討ちにする方法」から「年上の女の前でヘルマン・ヘッセを朗読する術」まで教えてもらった恩義があったので、その日からわたしはずっと「曲者志向」なのである。
ドリフターズの中で「曲者らしさ」を唯一感じさせてくれるのは荒井注さんだった。全員集合の寸劇を見ていても他のメンバーのギャグなどには目もくれず、ひたすら注さんの「な〜んだ、馬鹿野郎」の出てくるタイミングを待ちわびた。茶の「ちょっとだけよ〜」なんか反吐がでるぐらい嫌いで音楽が流れ始めた時点でボリュームをオフにした。そして「な〜んだ、馬鹿野郎」はマイク付きラジカセに録音して何度も聞き、イントネーションを研究した記憶がある。こうなるともう「凝り性」を通り超して「凝り病」「偏愛」である。
「注さん」というあだ名をわたしにくれたのは高校2年の時のクラスメイト牧内さんだった。女性である。おそらくわたしの一生のなかで唯一のあだ名である。一生だなんて、わたしはまだ死んではいないが、まあ今後もあだ名を付けてもらえるなんてことはおそらく無いだろう。
「あだ名」というのは改めて考えてみると深いものがある。いじめや馬鹿にする意味でのあだ名はダメだが、愛称としてのあだ名は実はその当人にとって値千金のものなのだ。「あだ名」をもっているということは、その人をとりまく小社会の中で、その人が安定したポジションを確保できているという証であり、人気、存在感ともに充実している証なのだ。ちょっとおおげさだが、きっとそうなのだ。(と思う)
今思い出しても、その2年7組というクラスは実に面白い曲者揃いのクラスだった。ビートルズを教えてくれた園田君、小説家を目指し椎名燐三にかぶれていた安楽君、何だかひょうひょうとしていて良く分からない萩原君、学生運動に憧れている新聞部の古殿君、音楽の話をよくした有留君他、毛色が違うというのか個性的というのか、みんなそれぞれに自分の世界を持った連中が集まっていた。そして放課後、美術部の部室で制服を毎日洗濯しては屋上に干して昼寝をする小林君(わたし)である。
なんとなく男子校のようだった。女子だっていた訳だが牧内さん以外はあまり覚えていない。
何かの折りに「な〜んだ、馬鹿野郎」と言ったのだろう。それが実にいいタイミングだったのか、全員が嫌っていた教師に対して言ったのだったかは覚えていないが、わたしは大いに受けてその日の内に「注さん」になった。
男どもは「注!」「注!」と呼び捨てにするので、わたしはそこでも「な〜んだ、馬鹿野郎」を連発した。他人のふんどしで相撲をとっているようで気が引けたが、別に人気取りで言った訳ではない。自然に練習の成果が出てしまったのだ。これも「芸は身を助ける」一例だ。まあそんなことはどうでもいいとして、その日を境にわたしの曲者としてのポジションは確立した。
さらにだ、わたしは17歳のくせに今(51歳)とほとんど同じ顔をしていたこともあって、その後は「注さん、相談があるの」とか「注さん、お願いなんだけどさあ」とほとんど若年寄りのような存在になっていった。自分は失恋ばかりしていたが、他人の恋だと何故か「壷」が見えたりしてわたしの助言は定評があった。美術部の部室で、わたしは毎日他人のために「恋の触媒」のような生活を送っていたが、まあそれはそれで面白く、わたしは満足だった。
2年7組はほとんどそのままのメンバーで3年生になったので、あいかわらず「注さん」は健在だった。「8時だよ、全員集合」ではもうあまり荒井注さんはギャグを飛ばさなくなっていたが、わたしは相変わらず「な〜んだ、馬鹿野郎」と言い続けていたような気がする。
高校3年の秋に、わたしにも他校の彼女ができたが、牧内さんをはじめ全員が面白がってお祝いをしてくれた。
受験のために上京したのは、校内でわたしが最初だった。2月の受験なのに年が明ける前の12月には鹿児島を離れた。わたしを見送るためにたくさんの仲間が西鹿児島駅のホームに集まり、特急電車が動き出すその瞬間、全員がわたしに向かって「な〜んだ、馬鹿野郎」と叫んだ。
ガラス越しにわたしも叫んだ。柱の陰でひとり隠れるようにわたしを見送った「秋にできた彼女」は「悲しくて泣きたかったけどおかしくて涙が出た」と後日その時の様子を語った。
2年程前に「東京鶴丸会」という、我が母校「鶴丸高校」の関東在住者の大同窓会に出席した。1期生から50何期生までが一同に集う大々的なものだ。おまけにわたしは、“元プロのシンガーソングライターの……”と紹介されて歌まで歌って(歌わされて)しまった。アトラクションみたいなものだ。辛島美登里も鶴丸高校出身だが“ギャラが高くて頼めなかった”らしく、わたしにお鉢が回ってきただけの話である。
座が一段落し、重責を果たして疲れきって座っていると一人のご婦人が近づいてきて遠慮がちにわたしに話しかけた。
「注さんだよねえ、知らなかったあ! 歌手なんかやってたなんて、小林注でレコード出してればみ〜んな買ったのに」
そのご婦人は、かつての同級生だった。当たり前だが48歳ぐらいに見えた。さすがに「な〜んだ、馬鹿野郎」は出さなかったが、わたしは30年振りにしばし「注さん」になった。
「レコードを出したこととかを誰にも知らせないところが注さんらしいなあ」
そうなのだ、わたしは当時“日本のゴッホ”を目指していたので、みんなには「注は今頃は“イッポ”ぐらいにはなってるかなあ」ぐらいに思われていたはずなのだ。
彼女はそれからしばらくの間、誰々の力を借りればもっとたくさんレコードが売れたかも知れないのにとか、南日本放送に知りあいのディレクターがいたのにとか、どうして鹿児島や地位のある先輩たちや組織の力を借りようとしなかったのだ等、余計なお世話のオバハン代表になって思い切りしゃべりまくった。 チッ! そういうのは嫌なんだよ! デビューしたことをわたしは両親にだって2年間知らせなかったんだよ、まったく「な〜んだ、馬鹿野郎」ってな感じである。
ブフフ・ブフフと笑うだけのわたしに溜息をひとつ投げて、彼女はあの頃の仲間たちの、今の「曲者振り」を教えてくれた。
いいぞ、いいぞお、みんないいぞお、曲者たちのお楽しみはいよいよこれからだ馬鹿野郎。
荒井注さんも小林注さんも今はいない。
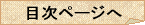
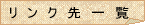
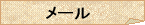 ・
・

