「 出世魚 」
ブリは幼魚の頃はワカシと呼ばれ、成長するにしたがってイナダ→ワラサ →ブリとなる訳だ。同様にボラなどもハク→スバシリ→オボコ→イナ→ボラ→トドとなる。そんな事は知らなくても実生活には何の支障もないが、幼少の頃何度となく繰り返し教え込まれたせいか、わたしの頭の中にはしっかりとしみついていて離れない。
出世魚の話にかこつけて男の一生を何のかんのと説教をするのはだいたいは母方の叔父たちだった。昭和30〜40年代、鹿児島というチョットだけ封建的な土地柄のせいもあったのだろうが、まあ“立身出世”は男の目指すべき一番のこととして教えこまれた。
「みちひろ君は一生懸命勉強して名をあげて、早くブリにならんといかん。総理大臣になって国を動かすような男にならにゃあいかん。それにだ、何としてでも薩摩隼人として西郷どんの無念を晴らさにゃいかん」
アナクロな叔父たちはとんでもないことを言い、明治維新であんなに薩摩はお国のために働いたのに、その後総理大臣一人出せないで誠に残念であると嘆いてみせた。当のわたしは、というと「総理大臣がブリだったら国民はどうしたらいいのだろうか」と妄想していたし、小学4年の時に隠し持っていた吉永小百合のブロマイド(お菓子のオマケだった)を姉に取り上げられて捨てられてしまったことで姉と死闘を演ずるような軟派な子供だったので、西郷どんどころか連れの犬の小便にも及ばないのだった。
母方の叔父が5人いて、皆血の気が多く、中央(関東)へ出てそれぞれ出世しようと努力しているようだった。ちなみに母方の旧姓は「鮫島」なので先祖はおそらく南海の海賊であっただろうと推測される。叔父たちは道路公団や生保、公務職で日々「ブリ」を目指していた。何年かに1度しか帰省しないくせに、甥のわたしをつかまえては「偉くなれ偉くなれ」と発破をかけるのだった。鹿児島男児たる者「常に上を見よ!」という事だったのだろう。わたしは幼少の頃目つきが悪かったが、何かやらかしそうな“曲者”の要素があると勘違いされたのかも知れない。今は目尻が垂下がっている。
叔父たちの説教を受けたおかげで、わたしは多少勉強した。いつか叔父たちのように東京に出て、それがどんな事でということはまだわからなかったが、世間に対して勝負をしてみたかった。何ででもいいから有名になってみたかった。井の中の蛙は誉められすぎて、自信過剰の殿様ガエルになった。叔父たちの言動にまんまと洗脳されてしまったようだった。
わたしはある日突然事件を起こした。大袈裟ではあるが、わたしのこれまで人生の中ではかなり大きな事件だ。わたしは父親の背中を蹴ってしまった。
父は一生涯を「平」の小学校教員で通した。師範学校を出た後、19歳で大陸に渡り、朝鮮の釜山辺りでも教鞭をとっていたらしい。終戦の折り、朝鮮人の若者たちが次々と日本人を襲うなかで、分け隔てなく朝鮮人にもやさしく接し続けていた父にだけは、彼ら(教え子)も刃物をふるわずお辞儀をして通り過ぎて行ったらしい。引き上げ後は鹿児島の小学校に落ち着き、引き続き教鞭を取っていた。弁当を持って来れない子供に蒸し芋を配り、休みの日には子供たちを家に呼んで無償でソロバンを教えていた。
父は一貫して平和主義者だった。体も小さく兵役検査も乙種合格だったらしい。一切の争いごとを嫌い、不平不満は自分の中で消化するのを待つタイプの性格だった。晩年の顔はガンジーそのものだった。わたしは一時期、そんな父がはがゆくてしかたが無かったのだ。
教員たちの世界も結構生臭く、田舎だったせいもあるが喧嘩・女問題・金・出世・派閥・その他のことで嫉妬や恨みが渦巻き、酒の席などではそれらが一挙に爆発してしまうようだった。我が家に飲みに来る父の同僚の先生たちは他人の悪口を言うために遊びに来ていたようだったが、父はそんな話になると一気に酒のペースを上げ、自分だけ真先に酔いつぶれてみせるのだった。
父のそんな“無欲な聖人君子ぶり”を、わたしは反抗期の一時期、愚かにも非難するような言動をとったことがある。今でも胸が痛む。
「とうさんは何故、教頭や校長になりたいと思わないの? とうさんより若い先生がみんな出世していくじゃないか、そんなことでひとりの男として悔しくないのかよ! おれだって教頭の息子の方がいいよ」
父は悲しい顔をして机に向かって聞いていた。少し震えているようだった。わたしは殴られるのだろうなあと思ったがなぜかそんなこともなかった。父は黙って外へ出て、借りていた畑の草をむしった。
おそらく父はわたしの性格をよく理解していた。わたしの血の大半は母方の叔父たちに近い血であることもわかっていたはずだ。おとなしくてとぼけた子供を装っているが、実は好戦的で上昇指向の強い部分を持っていることも知っていたはずである。そして“静かな水面にわざと石を投げるのが好きな性格”であることも理解していたに違いなかった。わたしは生意気で頭でっかちで大人にちょっかいを出すような嫌な子供だった。
2〜3年離島か山奥の僻地で勤めれば、教頭ぐらいにはすぐなれるシステムであることをガキのくせにわたしは知っていた。「そうして欲しいのか」といった内容の父と母の会話をそれとはなしにいつも漏れ聞いていたのだ。母は多少は出世に色気のある人だったようだ。しかし父の結論はいつも同じだった。「子供(わたしたち)の教育のためには僻地には行かない。家族はいっしょに居なければならないので単身赴任は考えない」 というものだった。父は言葉で自分の気持ちを表すのが極端に下手だったが、その分異常にかたくなな人であった。
世間一般的に“父親が偉大過ぎて息子たちが苦労する”話をよく聞くが、わたしの場合、父親がやさしい人過ぎて苦労した、ような気がする。父親の葬式で近隣の人々が口々に「神様のような人でしたなあ」と言ったが、わたしとしてはどうお礼の言葉を述べていいのかわからなかった。種類はちがうが偉大という意味では同じである。わたしは父を越えられない。
現在のわたしは、食うために仕事はしているが出世などとはまったく無縁となり瓢々としている。それでもまだ音楽・美術・作文……と、やりたいことが山ほどあってできることなら少しずつでも向上したいという気分も残っている。しかし座右の銘が「棚からぼたもち」だから、おそらくダメだろうが……。
人を騙さず・欲を出さず・他人を泣かさず・自分に恥じず・盗まず・殺さず・欺かず・雨の日も風の日もいつも静かに微笑んでいる人になりたい……なんて言っていたら何もできなくなってしまうではないか。
「おいしそうな寒ブリがありましたから今日はブリ鍋にしましたよ」と妻はいうのである。わたしは切り身を箸でつまみ上げ「お前もブリブリ言わして出世してきたんだなあ、たいへんだったなあ」とつぶやくのである。妻は「?」といった顔でわたしを見る。わたしは応えず、しばし父の、母の、自分の、娘の、妻の、その他諸々の人生を思うのである。
「それはブリ、あなたは大ボラ」妻は解っているのか解っていないのか解らないようなことを言った。
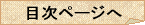
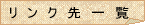
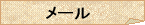 ・
・