「 砂山 」
<シーン その1>
修一が12歳の夏、その村の海辺では奇妙な遊びが流行っていた。堤防を越えてさらに海側に広がる砂浜の上で、皆憑かれたように砂とたわむれていた。
美しい海辺だった。どこまでも続く白砂のカーブ、7つの村にまたがる松林、波うち際は無数の宝貝やさくら貝であふれ、引き潮は沖合い1Kmまで歩いて行ける干潟を作った。
誰が始めたことなのかはわからなかったが、ある日「城」の数は30を越えていた。大人たちの姿こそなかったが小中学生から20歳ぐらいまでの若者たちが大小さまざまな砂の城作りに熱中していた。
修一たち小学生が作るものはたかが知れている。固く叩いた砂の立方体に横穴を空け、凱旋門だ、要塞だと騒ぐ程度である。中学生たちがやっと縦横1mほどの“城のようにも見える砂の固まり”を作って威張っていたが、ある日そんな中学生たちもため息をついて感心する程の本物の「城」が出現した。
作ったのは19歳の青年だった。修一の家の川向うにある養豚場の一人息子だった。
その青年がいつから着工したのか、もう何日目であるのかはわからなかったが、それは今まで誰も見たことのない程の巨大な建造物になっていた。まったく関心を示さなかった大人たちが、噂を聞いて夕涼みがてらそれを見に来るようになった頃、彼の細工は10m四方の大きさになっていた。
あきらかに日本の城ではかった。中央に縦横高さ1.5mほどの神殿らしきものがあり、そこから放射状に塔や塀や屋敷が続き、まるで何千分の一かの古代の街の縮尺模型のようになっていた。
建物の尖った角の部分は卵の白味を塗って固めてあるらしい、という噂もあった。芯棒が通してあるらしいことはわかったが、神殿の円柱はどんな方法で砂を固定してあるのか推測さえもできなかった。青年が夜中にヘッドライトを点けて作っているのを見たという者もいた。
農作業を終え夕方から浜に来て作業をするその青年と、修一は一度だけ口をきいた。顔は見知っていたが声を聞くのは初めてだった。
「これはどこのお城な?」
「わからん」
「…………」
「いつまで作っとな?」
「わからん。けど、もうそろそろすることはなか、あとはひっこわすばっかいしかなか」
12歳の修一は青年を少し恐ろしいと思った。「もう壊すこと以外にすることが無い」青年は強い口調で腹立たしそうにそう言ったのだ。
青年のその言葉は修一が村を離れてからも、さらに成人してからも、ずっと修一の記憶の片隅に残った。
それから2年後、その青年は仕事のかたわら見よう見真似でコツコツと「能面」を彫り、南日本美術展で県知事賞を獲ったがその直後に養豚場の梁で首を吊った。
<シーン その2>
「家まで送ってくれるの?」
由美は静かにまた話し始めた。西にかすかな赤味を残す藍色の空に、コウモリが飛んでいる。
「ああ」
修一は苦笑いをした。二人がまだ恋人同士だった頃でも、彼女を家まで送ることはそう多くなかったのだ。
「最後だから?」
「ああ」
二人を終着まで運んだ路面電車がベルを鳴らして折り返して行った。横断歩道用の信号が点滅しはじめる。
「東京の彼女はいい人なの?」
「ああ」
「奇麗な人?」
「ああ」
街灯に群がる羽虫を食べ損なったのか一匹のコウモリが急降下して二人のすぐ横を飛んだ。
「なんであの店にいたの? 会えると思った?」
「ああ」
「未練ったらしいのね?」
「ああ」
遠くに汽笛の音が聞こえた。川崎行きのフェリー「サンフラワー」が港を出て行く。
「無理矢理だったよね」
「ああ」
「わたしが東京へは来ないってわかったから?」
「ああ」
「だって、無理だよ、母さんひとり残しては。修はまだ学生だし」
「ああ」
一人の女が二人に軽く会釈をしてすれ違った。二人の高校時の同窓生だった。
「ああ、しか言わないのね」
「ああ」
満潮だった。川の水は動かない。大きなボラが跳ねて音をたてた。
「写真とか手紙とか返したいけど、あの後すぐ燃しちゃったから」
「ああ」
「“こっちで女作ります”はないよ」
「ああ」
「わたしのためって……」
「ああ」
街灯のジュラルミンのポールに大きなヤモリがへばり付いている。目の前に羽虫が来るのをじっと待っている。
「結婚するよ?いいの?」
「ああ」
「本当にいいの?」
「ああ」
「ああ、なの?」
「ああ」
鉄橋の上を列車が火矢のように飛んでいった。
「二度と会うことはない……」
「ああ」
「先にしあわせになる……」
「ああ」
「……」
「ああ」
自宅へ通ずる路地の入り口で、由美は修一を悲しくにらみつけてそのまま奥へ駈け込んで消えた。
修一は最後まで「ああ」しか言えなかった。それでよかったのだ、と思った。12歳の夏に村の砂浜でみた巨大な砂の城と、そして狂ったように何事かを叫びながら自分の作った城を木刀でたたき壊す青年の姿を思い出していた。秋の気配の中でただの砂山になってしまった城を思い出していた。
(完)
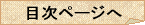
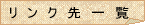
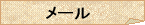 ・
・