「 白い少女 」
命にかかわるような恐い経験、というのは何回かある。
帰宅途中で2mうしろの電柱に雷が落ちた時もそうだし、カブでの旅の途中に後ろからきたトラックにハンドルを引っかけられてコントロール不能の状態で50m走った時も「ア! 俺はここで死ぬんだなあ」と思ったものだ。
大腸癌のときも「35歳はちょっと早い気もするが、まあここまでは面白い人生だったなあ」と遺書を書いたし、手術後の黄色いお花畑は臨死体験だったような気が今はする。
と、まあ人並みにそちら方面の恐い思いは何度かしたことはあるのだけど、いわゆる“身の毛もよだつ”とか“草木も眠る丑三つ時”系の恐怖体験というのには今までまったく縁が無かったのだ。
高校1年の時に父方の祖母が亡くなって、葬儀の最終段階「火葬場」へ行った。もちろん悲しかったのだけど、わたしは“一人の人間の死後の対処”の方により強い興味を抱いていた。
先程まで泣いていた者たちが火葬場に着いた途端に急に事務的な行動及び言動になったような気がしたのだ。
「焼き上がりは何時の予定だ?」
「待ってもらっている間のお茶菓子とかは手配できてんの?」
「お骨を家に連れて帰ってからの寿司の数、追加しといてよ! 人が増えちゃったからさあ」と、そんなようすなのだ。
わたしは控え室には戻らず、焼き釜の前で線香を絶やさぬように番をしながら、火葬の着火直後に死人が膨れて棺桶から立ちあがるというのは本当だろうか、と釜の中を覗き穴から見たりした。炎がまぶしくて何も見えなかったが、ふと自己嫌悪を感じて視線をそそらすと左前方に外に出れる小さなドアがあり50Cmほど開いたままになっていた。わたしは新鮮な空気でも吸おうかと、こそこそと歩みより外へ出てみた。
そこにあったのは人骨の山だった。おそらく何十年も前に土葬にされたものを、近日中に“焼き直す”ためにそこで順番待ちをしている骨たちであるようだった。うず高く1mほどの山になったそれらは頭蓋骨も大たい骨も真っ黒で少し濡れた流木のようだった。そして何十人分かの骨が入り混じり、どれとどれが対であるのかどれが男でどれが女であったのか、などということは推察すら不可能なようだった。横にはハンマーが置いてあり、焼くまでには細かく砕く予定のようでもあった。
「ああ、人は死ぬとこのようなものになるのだなあ……」わたしは恐怖も嫌悪も感じることなく、ただそう思った。そんなものになってしまうことに涙が出た。 以来、わたしは霊とか幽霊とかには興味がなくなった。興味のない者には先方も興味がないらしく、両者の間には「縁」がなかった。
わたしが「白い少女」に会ったのはもう2日も降り続いている雨の夜だった。秋の長雨というやつである。
駅から歩いて帰宅すると、自宅の手前50mほどのところにセブンイレブンがあり、その対面にせんべい屋がある。草加が近いので大きな七輪での「実演手焼きせんべい屋」があるのだ。そのせんべい屋の前に彼女は傘もささずに立っていた。
わたしは会社の事業計画の途中修正及び挽回案出しでかなり疲れてはいたのだが、彼女をしっかりと視認していた。距離にして30mだ。
「こんな時間、こんな雨の中であんな小さい子供が一体何をしているのだ」と意識して見たのを今でもはっきりと覚えている。
「そうか、母親か誰かが車ででも迎えにくるのだな、それを待っているのだな」ぐらいの気安さではあったのだけど、とにかくはっきり見たのだ。
そこへわたしの後方から車が走ってきた。ああ、迎えがきたな、と思った。しかしその車は1度も止まることなく、そのままのスピードで走り去ったのだ。そして気付いた時には白い少女は消えてしまっていたのである。どこを探しても、辺りを見回しても彼女はいなかった。
どこか近隣の家に入った様子もなかったし、ましてやあのスピードの車に乗り込んだなどとは到底考えられない。しかしわたしは首をかしげながらもあまり深く考えることもなく帰宅した。
「さっきそこで変なことがあったんだ」
わたしはことの顛末を妻に話した。妻は少し考えた後、田中邦衛のように口をとがらせて言った。
「その子は“あっちの世界の子”ね。あなた鈍感ねえ、おせんべい屋さんの裏には30個ぐらいお墓があるし、何かあなたに聞いて欲しいことがあったか、あなたに警告したくて“あっち”から来たんじゃないの?」
わたしは背筋をゾクゾクさせなから「ふざけんなよ、馬鹿!」と笑った。
「わたしも色々あったから、そういうものにすっかりドライになっちゃったけど、最近あんまり醒めちゃいけないような気がするのよお」
妻も母親の長期介護、そして死、と色々苦労したせいか、わたしと同じように霊とか幽霊とかをまったく怖がらない人間になってしまっていた。
「あなたが、霊とか来世の話になると、馬鹿にしちゃってまったくとりあわないから忠告にきたのよ、文学とかには大切なんじゃないのお、そういうの? せっかくのあなたの才能を埋まらせたくないと思って、まだまだ不思議な世界が本当にあるんだよって教えに来たんじゃないの?」
「文学? あなたの才能?」ブフブフブフ、妻は天才的な誉め上手なのであった。
「そうかも知れんなあ」わたしは少し怖くなった。
せんべい屋の前を通る度に「出ておいで、何でも聞いてあげるよおじさんが」とつぶやくのだけど、白い少女は気持ち悪いのか恐いのか、あれ以来1度も会ってくれないのだ。人は死んだら一体何になるのか、彼女から実体験を聞きたいのだけど、それを小説にして大儲けしようというわたしの魂胆を見透かされているらしいのだな、これが。
幽霊にはまったくかなわない。
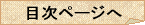
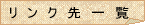
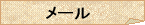 ・
・

