「 なりすまし 」
ロバート・デニーロが好きだ。なんといっても青春期に観た「タクシードライバー」は衝撃的であったし、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」などは時間があれば今でもたまに観る。しかしDVD2枚組なのでいつのまにか眠ってしまい、気がつくと終わっていたりするので最初の方だけ何度も観ているような気がしないでもない。音楽もいい。エンニオ・モリコーネなので2年ぐらい前のNHK大河ドラマ「宮本武蔵」と同じパン・フルート多用パターンの元祖だが、まあ大好きなのだ。
先日も気が向いて「タクシードライバー」をつまんで所々観た。「こんなタクシー乗ったら、けっこう恐そうだぜ、クックッ」などと思っていると記憶がよみがえってきた。わたしはまたクックッと笑った。
オールナイト・ニッポンでDJをやっていた頃のことだ。放送が終了した後、しばらく次回の打ち合わせなどをして帰路につく訳だが、バブリーな時代だったこともありスタッフも含めてタクシー(ハイヤーだったような気もする)で自宅まで送ってもらえるのだった。わたしは埼玉に住んでいるので、有楽町から普通にタクシーを利用すれば¥7000ぐらいかかるし、すでに電車も走っている時間なので申し訳ないなあ、といつも思うのだがなんとなく芸能人を実感できる瞬間でもあって、多少は気分がいいのも又事実だったわけである。
ある日、いつものように放送を終えてタクシーに乗り込むと、非常に“話し好き”の運転手であるらしくすぐにわたしに話しかけてきた。
「今のデージェー(DJ)の人はあんまりまだ話が上手じゃないですなあ」
「……ん?」
「小林なんとかというチンガー・ソング・なんとかというデージェーの人」
「ああ、ディージェーのシンガー・ソング・ライターの人ね」
わたしはムカツキ49%、おかしさ51%でつい笑った。運転手は完璧にわたしをスタッフだと思っているようだった。
「最初の水戸黄門の曲が先ず合ってないだすなあ」
「ああ、そういうもんですかねえ?」
「ああいうのは誰が決めるんですか? 小林なんとかさんが決めるわけじゃないだしょう?」
「まあ、そういうのはわたしらスタッフがねえ」
「あ、そうかそうか、失礼なこと言うてしもただすなあ」
「あいや、いいすよ、勉強になるっすよ」
わたしは小林倫博のマネージャーになりきることにした。クックッである。
「ところで、どういうところがダメですかねえ小林の?」
「いいやあ、ダメってえ訳じゃないだすよ、ただね、無理をすてるのがラジオ聞いててもわかるだすよ」
「無理してますか?」
「ああ、無理すてるな。ハーハー言ってる。そんなに気張ってしゃべらんでも時間も時間なんだし、ゆっくりしゃべってればいいんだすよ」
ムムッ、運転手はなかなかの達人らしかった。
「この時間は眠気覚ましに、なるべくニギニギしくって方針があるんすよね」
「うるさいぐらい賑やかでも、つまらんもんは眠いがな、その反対もあるが」
「まあ、そうですねえ」
「歌はまあまあ上手だし、チンガー・ソングとしてもええもん持ってるんでね、普通にしゃべるように言うてくださいよー」
来た来た、生意気になってきた、いいぞいいぞー。わたしは嬉しくなってきた。
「真面目な人なんだしょうなあ、コバちゃんは?」
「コバちゃん? ああ、小林ね、そうねえ、真面目な人……ですねえ」
「真面目過ぎてもいかんのだすなあ、芸能人は」
「そうすねえ、俺も小林にたくさん遊ぶように言ってるんですけどねえ」
「コバちゃんは結婚しとられるだすか?」
「いや、まだねえ」
「だったら、もっと遊ばにゃーいかんだすな、おたくマネージャーならそんな話もたまにはするだすか?」
「ええ、まあねえ」
「トルコとかキャバレーとか色々遊びに連れて行った方がいいだすな」
「トルコですか?」
「トルコですがな、マネージャーさんなんか全国区だしょう?」
えらいことになってきた。真剣に嘘をつかないとばれそうだ。わたしは下半身にまったく自信がないのでそっち方面の話はちょっと苦手だ。地方のイベント屋などはコンサートの打ち上げの流れで「接待するから行こう行こう」と誘ってくれるのだが、わたしは下半身の代わりに頭を固くしていつも断り続けていた。仕方なくわたしは、わたしの本当のマネージャーから聞いていた風俗関係の武勇伝を借用して語りまくった。そのマネージャーはわたしの後輩にまで手を出した強者だ。そのことではケンカになったこともあったが、まあ悪い男ではない。
「ガハハハ、流石だすなあ! おたくの方がよっぽど面白いだすなあ、デージェーしたらええだすなあ、そんなオッパイの娘もいるだすか」
「ラジオでこんな話できないっすよ」
「それもそうだすな、ガハ!」
わたしはもうすっかりなりきっていた。
「小林にも言ってるんですよ、ほんとは助平なくせに気取ってんじゃねえって」
「そうだすなあ、さっきも恋の悩みのハガキに糞真面目に答えてたすなあ、ああゆうのはちょっと臭いだすなあ、“走れ歌謡曲”に変えようかち思いますなあ」
「まあ、まあ、オールナイト・ニッポンを最後まで聞いてやってくださいよ」
「ハハッ、まあなあ。それとなあ、あんまり腰が低いっつうのもどうかなあと思うなあ、いい人かも知れんが慇懃無礼ってこともあるさあね」
「そうなんすよねえ、八方美人なんすよねえ、やさしけりゃいいってもんでもないっすよねえ、それじゃあ売れないっすよ」
それからしばらくの間、わたしと運転手は“これから先どうすれば小林がまともな芸能人になれるか”を語りあい、わたしは小林の嫌いな部分を指摘しまくった。
「小林によ〜く言っときますよ、ありがとやんした」
わたしはタクシーを降り、Uターンして行く運転手に手を振った。静かに自分自身に戻ってゆく不思議な感覚を楽しみながら、一体誰のふりをしていたのかわからなくなってしまった。
そして一瞬、わたしはけっしてマネージャーになりすましていたのではなく、「こういうタイプの人間だったらよかったのになあという架空の自分」になりすましていたような気がした。
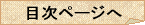
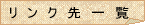
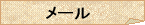 ・
・