「 靴の履歴 (オムニバス) 」
①「白い花」
「鹿児島の人たちって、みんなパンツ1枚で、上半身は裸で、ジャングルの中を走り回っていて、全員西郷さんみたいに犬を連れて歩いているんでしょう?」
東京に出てきたばかりの頃、そんな質問をした高橋という女がいた。冗談で言っているのだろうと思ったが真顔なので、もしかすると本当の馬鹿女かも知れない、と情けなくなった記憶がある。確かにジャングル風呂というのもあるし、犬を連れた西郷どん似の人もたくさんいるがあくまで観光用だ。
しかし一部本当のこともある。わたしは小学3年生まで、ずっとパンツ1枚で上半身裸で裸足だった。そしてジャングルではなかったが、村の山野を「ア〜ア・ア〜!」とターザンのように叫びながらアケビの実を求めて跳びはねていたのである。
村の子供はみんな裸足だった。道に落ちている牛馬の糞尿など気にもせず毎日元気に遊び回っていた。雨の日はグシャグシャの水溜りにわざと飛び込んで泥水を跳ね飛ばした。泥水で汚れた茶色いパンツは名誉だったし、足裏のツボを砂利が適度に刺激してみんな健康だった。
「靴はみんな持ってはいるけど、楽しいし気持ちいいから裸足なんだろう」
わたしはそう思っていた。しかし当時まだ終戦から15〜16年、家に電気の引かれていない貧しい農家の子供が2人いて、その子たちだけが何かの式典で裸足なのを見てわたしは泣きたくなった。式典なんかしなければいいのにと思った。いっそのこと靴なんか法律で禁止にすればいいと思った。
お山の大将だったわたしは裸足でない子を仲間はずれにした。とくにその2人の前では裸足であることを鉄則にした。
「裸足は気持ちよかなあ」などと言ってみたりした。
「寄生虫がわくので、靴を履きましょう」
小学3年の時の、学校をあげての「年間努力目標」だった。現代では笑い話にしか思えないだろうが、事実回虫やぎょう虫のいる子供が多かったのである。
そしてある日、それは天皇陛下が乗った列車に旗を振りに行く日でもあったが、全校生徒に「今日からはこれを履くように」と白いズックが配られた。それはまぶしいほどの白さで、休み時間に教室の窓から校庭を見ると、まるで小さな白い花がたくさん、たくさん咲いたように見えた。例の2人の友達も白い花になった。
しかし終業の鐘が鳴ると、全員ズックを机の下に放り込み、また裸足で笑いながら帰って行った。
我が家では定期的に「カイニンソウ」というのを飲まされた。海草を煎じた虫下しだ。真夜中に1度起こされて飲まされるのだが、これが実に気持ちの悪い味だった。
10歳のわたしはカイニンソウを飲むぐらいなら靴を履こう、と思った。
②「48個のイボイボ」
中学の頃、わたしは実に足が速かった。100mをだいたい13.5秒ぐらいで走っていたので、体育の教師はわたしに再三陸上部に入るように言った。が、わたしはその頃はまだ「医者になって無医村の人々を救いたい」などと又別の意味で馬鹿な夢を抱いていたので、そうはしなかった。
さらにわたしにはある“理想像”があって、それは月光仮面なのだった。どういうことかと言うと、どこの誰だか知らないが疾風(はやて)のように現れて美味しいところを全部持っていってしまう、というパターンだ。
話はそれるが「笑点」の座布団運び「山田隆夫」は、その昔「ちびっこのど自慢」という公開テレビ番組で客席からステージに飛び入りで上がり、いきなりチャンピオンになった。わたしはリアルタイムでその番組を観たが、こういうのは実にいいなあ! と思う。アマチュアがプロに勝ったりするのはしびれる。
というわけで、一般生徒のわたしが陸上部の連中より足が速いというのが理想的なのだが、ものごとはそう簡単にはいかない。陸上部には沼田という男がいた。わたしは中学から身長が伸びていないので当時は大きい方だったが(164Cm、今は162Cmに縮んだ)沼田は175Cmもあったのだ。中学2年でだ。100mを12秒代で走る県下でも有力な中学生だった。1歳年上だという噂もあったがそんなことはどうでもいい、わたしはとにかく沼田に勝ちたかった。
わたしは策の無いまま体育祭を迎えようとしていた。賭けのつもりで スタートの練習ばかりをしていたが、戦うのは互いにリレーのアンカーとしてなのでスタートの練習はあまり意味の無いものだった。それと「靴」が問題になるような気がした。沼田はスパイクシューズを履いていた。
体育祭当日、わたしはスパイクシューズに対抗すべく(?)白いソックスを膝までおもいっきりズリ上げていた。そうするとふくらはぎが締まって、もっと速く走れるはずだと憧れのマユミちゃんが言ったのを真に受けたからだ。
わたしの組が1位できた。沼田の組が2位だ。その差2m、バトンはほぼ同時に受けた。わたしの右後方でザクザクと沼田の足音がした。う! 速い!並ばれた!
ゴールした時、わたしは沼田のスパイクの底のイボイボをみた。3mは離されていたようだった。イボイボの数は片方で24個付いていたように見えた。両足で合計48個だ。絶対にかなうはずがなかった。
③「戻ってきたNIKE」
米空軍のパラシュート素材を使ったということで、70年代の中頃に一躍大人気になったNikeのスニーカー、とにかく軽かった。
わたしが特に好きだったのは、水色の本体に白や黄色のナイキマークがベタリと縫い付けてあるモデルだった。アロハっぽいシャツに洗い晒しのジーンズ、ジーンズはLevi'sではなくてLeeでなくてはならず、そしてスニーカーは前述の水色のNikeだ。当時シンガーソングライターとしてユイ音楽工房というニューミュージック系のプロダクションに所属していたわたしは、「風」のショーヤンやクボヤンの真似をしてそんなスタイルで原宿を歩いたりしていた。
つい先日も例の水色ナイキをはいた中年オヤジを見たので現行モデルなのかもしれないが、型番や名称というものにはまったく疎いので、その靴の名前はわからない。ジーンズだってその時(22歳)初めてはいたぐらいのわたしが、LeeだのLevi'sだのと語るのもおかしいが、まあとにかくNikeのスニーカーは軽快だった。
非常に唐突だが、そんなある日わたしは恋をした。わたしは女性を好きになるとすぐに結婚したくなるタイプなので、どうしたら相手がその気になるか必死に考えるのだ。だって、結婚する気はないけど楽しくつきあいましょう、って女性も多いから困ってしまうのだ……よ。で、プロポーズのような、そうでもないような口説き文句の小道具として、わたしはそのNikeのスニーカーをつかったのだった。“井上陽水もびっくり”の恥ずかしい行動である。
「この軽やかな靴を履いてぼくと人生をいっしょに歩いてくれませんか?」
わたしは真顔でそう言ったのだった。その場で吹き出す女性も多かったが、ちゃんとまともに受けとめてくれる女性もいてキザな台詞はキザなりに相手のこころを動かしたりもした。しかしまあ、そうそううまくは行かないのが男女の仲でもあるわけで、わたしがツアーに出ている間に別の彼氏を作ってしまったり、煙のように消えて無くなってしまう女もいて、わたしはその度に悲しい陳腐な歌をつくったのだった。
そして捨ててくれればいいものを、彼女たちは靴を返してよこした。
「この靴でいっしょに歩いて行きたかったけど、いっしょに歩く時間が無さ過ぎました。さようなら、靴はお返しします、その気はもうナイキ」
わたしはあまりの悲しさに、つい靴の匂いを嗅いだりしたが(しない、しない)、結局わたしの元には3足のNikeが戻ってきた。そうです、御察しの通りわたしは3回も同じ「手」を使ったのである。もしかすると彼女たちは、わたしのそんな“どこか常識の欠落した人間性”に愛想を尽かしたのかもしれない。きっとそうだ。
そう考えると、妻を大事にしなきゃいかんなあ、と思う。なぜなら妻にあげた水色Nikeはもどってこなかったのだから……?
そうなんです、正直に言うと同じ手を4回使いました。
④「GT・ホーキンス」
「破水しました。今日生まれます」
妻は静かにそう言った。わたしは何をどうしていいのかわからず、ただ荷物を持って黙って彼女のあとをついて歩いた。アパートから病院までは200mほどしかなかったが、その距離をわたしは彼女との歴史を振り返りながら歩いていた。
わたしは彼女を友人から奪った。友人はわたしの前から姿を消した。そしてまた、わたしは彼女を母親からも奪った。義母はわたしを世界一身勝手でいいかげんな男だと思っているはずだった。
そしておそらく、わたしは彼女からもすべてを奪った。彼女にとって、わたしと結婚したことは本当にいいことだったのだろうかといつも自問した。彼女には“もっと楽な結婚”がふさわしかったのではないか、と考えたりした。わたしたちは“駆落ち結婚”だった。
病院にたどり着くと200mの距離とはいえ安心したのか、妻はベッドの上に横たわり目を閉じてしまった。強い陣痛はまだ無く、緊迫感もない。
ボーッと廊下につっ立っているわたしに、百戦練磨のいかにも豪気そうな婦長が言った。
「病気じゃないんだから〜! それにまだすぐには生まれないんだから〜、どっかで2〜3時間暇をつぶしていらっしゃいよ〜」
夫が廊下でオロオロしていると分娩室でオギャーと声がし、やがて看護婦が赤ん坊を抱いて「女の子ですよ」などと言いながら出てくる……というわたしの“父親になる日”のイメージは見事にくつがえされた。わたしは妻に声をかけ外に出た。
予定日をすでに1週間ほどオーバーしていたので、いくら絶縁状態とはいっても義母も気にしてはいるだろうと思い、こういった場合はやはり電話ぐらいはしておいた方がいいのだろうか、などと考えているうちに足はイトーヨーカドーに向いていた。まったくもっていいかげんな男だ。エスカレーターで上昇していると3Fの靴売り場に目を引かれ慌てて飛び降りた。
わたしはジッとひとつの靴を見つめていた。それがGT・ホーキンスだった。靴底はぶ厚く、車のタイヤのようだ。雨にも風にも負けずに生きて行くにはそれしかないような気分にさせられた。自分に今必要なのはこういう靴かも知れない、わたしは財布の中を確かめた。妻と子供を守っていくには値段は倍ぐらい高いが普通のやつよりゴアテックスのやつが良さそうだった。どうせ買うなら型落ちでもフラッグシップ物に限るぜ……、もうわたしの頭の中は靴一色、まったくもって自分勝手な男である。
1時間半ほど経って病院に戻ると、向こうから例の太っちょ婦長が走り寄ってきて叫んだ。
「イヤだ〜! もう生まれちゃいましたよ、どこ行ってたんですか、呑気な父さんねえ!」
「呑気な父さんって! あんたがどっか行ってろって言ったんじゃないですか!」
わたしは「訴えてやる」とか言いながら妻の元へ走った。
「股がちょっと裂けちゃったから痛いよ」
妻は口をへの字に曲げてデヘッと笑った。わたしは「アー、アー」というだけで頼りなかったが、それでも妻は安心したのか目を閉じて眠ってしまった。
ドアを閉めて隣の部屋に行き、わたしは我が子と対面した。それは文字通り“赤子”で、“タラコ”のようでもあり小さかった。
わたしは「小さいなあ、ひょっとするとこの靴の中に隠して、こっそり連れて帰れるかも知れんなあ」と軽い衝動にかられながら、左手に持ったGT・ホーキンスと我が子を交互に眺め、やっとクスクスと笑った。
⑤安全靴とモグラの生活
40歳は不惑のはずだが、わたしは48歳で惑いに惑って勤めをやめた。もう一度だけ何かに挑戦しようと思ったからだ。無知もあったが失業保険も使わないまま、何か「力いっぱい働く」仕事をしてみたいと思った。「一生懸命」ではない「力いっぱい」だ。できれば戸外がいいと思った。
で、川口にある土木建築の会社に入った。いわゆる土木工事作業員の派遣会社である。朝6時に事務所に行くと、今日はどこどこへ行くようにと指示され、電車で現場に向かい土木工事に従事する訳だ。仕事が終わるとまた事務所に戻り、その日の日当¥9000をもらう、といった仕組みである。
はじめて事務所を訪れた際、あからさまに変な顔をされた。つまり、今まで楽な仕事しかしていないサラリーマンに力仕事なんかできるかよ、というわけである。おそらく1日で根をあげる、と思ったのだろう。
「小林さん、悪いんだけどね、これ、決まりだから、すぐに辞めちゃったら無駄になるかも知れんけどね、一応決まりだからさ」
係りの人はすまなそうに棚から黒いブーツタイプの安全靴を取り、わたしの前に差し出した。¥8500だという。ほぼ1日の日当分である。わたしは苦笑いをしたが、なめられたことでちょっと悔しい気もしたので、結局作業衣までそこで買い¥14000ほどを初日に騙しとられた。だって、後になってわかったが、別にその場で買わなくても自分で量販店などで揃えてもよかったらしいのだった。
色々な現場に行った。あくまで通説だが賃金的にもランク的にも一番低いと言われる“土工”である。1日中、泥と土にまみれる仕事が多かった。建設中のビルの地下の、さらに鉄筋回りの機械でできない場所の泥のかき出しとか、狭い通路を使った荷上げである。50Kgの板材を担いでビルの7階まで階段を登る作業などを1日中やった後は自分が生きているのか死んでいるのか分からない程疲労し、小便さえ出なくなった。
新品の安全靴を履いているのが恥ずかしくて、わざとコンクリートにこすりつけて傷を付けてみたりしたが、1週間もするとそんな必要もなく十分に傷だらけで迫力のある汚い靴になった。作業衣もあまり洗わなかった。
一定の日にちが経つと、ある程度経験も積めただろうということで仕事場が固定された。とにかくガムシャラに働くので、現場での評判はよかったし、リーダーさんもわたしを気に入ってくれたようで推挙したようだった。
場所は府中近辺の高速道路、仕事はアスファルトの敷き更え工事である。“はつり屋”がコンプレッサーで古いアスファルトをどんどん壊してゆき、わたし(達)はその瓦礫をざるに集めダンプカーに放り込むのだ。1日中それのくり返しである。「急げ急げ、休むなよ、次!」 “はつり屋”は「壊してきれいにサラ地にした場所の数」で報酬が変わるので競争である。5グループの“はつり屋”がいっせいに競ってアスファルトをこわすのだ、残骸を手で回収するわたしたちはたまったもんじゃない。一応、厚い皮の手袋をはめてはいるが1日の終わり頃には手袋が破れ、気がつくと指先が血だらけになっていたりした。指でも落とせばギターもピアノも弾けなくなるなと思いつつ、まあそれもいいか、と思ったたりした。防塵の眼鏡とマスクをはめてはいるがホコリは体の穴という穴すべてに入り込み、へその中にまで黒くたまった。
ヤケクソ及びムキになって労働した。硬い安全靴のせいでかかとからアキレス腱の辺りは豆だらけになり炎症を起こして発熱、甲にはランチュウの頭のような血まみれのコブができた。それでも、それはそれでおもしろかったような気が今はする。
「本当に変な人ねえ、しばらくのんびりするんじゃなかったの? 何なの?」
妻はわたしを異星人を見る目で半分嘲笑していたが、朝5時には甲斐甲斐しく弁当を詰めて毎日わたしを送り出した。
相変わらず足は歩くのがやっとなほど痛かったが、多少慣れてきたのかその日の重労働から開放されて帰宅した後に、楽しみなことが一つ出来た。それは買い物であった。前の仕事では考えられないことだったが、夕方の6時半には帰宅出来たのでゆっくり風呂に入り、近所のスーパーマーケットにおかずを買いに夫婦で出かけて行くのだ。楽しみが無くなるから夕飯の準備を済ませておかないように妻には言い、あれこれゆっくりと自分の目で食材を選り好みした。
正確には酒の肴と言った方がいいが、これがなかなか癒される。そんな些細なことと言われそうだが、それがあることでわたしはどれだけ救われただろう、やっと人間に戻ったような気分になれるのだった。
さらに妻と缶チューハイを飲みながら、わたしはその日1日あったことや出会った人、仕事の内容を話した。そしていつのまにかその日の自分を動物に例えて話すのが恒例になった。
「今日は1日モグラだったぜ、土の中にいるようだった」とか話すわけである。
ぬかるみの中で作業をした日は「ムツゴロウ」になったし、1日中溝堀りの日は「オケラ」、鳶職人の手伝いをした日は「烏」になった。妻はわたしのボロボロの足を気遣いながらも涙が出るほど笑い転げ、わたしはジェスチャーまで加えて晩酌を盛り上げた。
一番長かったモグラの生活が終わり(高速道路の工事が終り)、また今日は猿だ、明日はゴリラだと日替わり動物生活に戻りそうになった頃、わたしの緊張感は突然途切れてしまった。もうとっくの昔に死んでしまっている父を再度「危篤」にして、わたしはその土木工事会社を辞めた。必ず戻ってこいよ、とリーダーさんは言ってくれ何度か電話ももらったが、傷だらけの安全靴は倉庫の中に放り込まれたまま2度と現場に出ることはなかった。
モグラの日々のおかげで、わたしはもう何も恐くはなくなっていた。体が動く限りは、いざとなれば何をしたって食ってはいける。もともと楽をしたいという気持ちなど微塵も無いのだ。残りの人生が何年残っているかは知らないが、どうせ癌の死にそこないである。オマケの人生である。本気で自分のやってみたいことだけに残りの寿命を使いたいと思ったのだ。
足の甲のコブは今でも残っていて、疲れた疲れたとわたしが愚痴を言いかけるとムズムズとかゆくなる。1日1文の誓いはどうした! ということらしい。
幸か不幸か、今まで色々な靴を履いてきたのでこの「靴の履歴」はまだ今後もつづくのである。
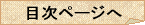
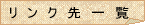
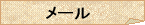
・