「 鎖の先 」
わたしは親に対して何々が欲しいから買ってくれとか、なになにをどうこうしたい等の要求をあまりしない子供だった。もっとも現代のように情報があふれていた訳ではないので単純にものを知らなかったとも言えるが、まあそんなわたしが自力ではどうすることもできず、重い重い口を開いて親にお願いしたことのひとつが「犬を飼うこと」だった。
ある日、小学3年生のわたしは学校のゴミ焼却所で黒い小犬を見つけた。雑種犬に違いはなかったが、足の裏の肉球まで実に真っ黒の可愛い小犬だったのだ。わたしは子供のくせに妙にこだわりを持った性格だったので、今後もし自分が犬を飼うことがあるなら絶対に大きな黒い犬を飼うことを心に決めていた。
黒くて精悍な犬と山や浜辺を一緒に走る光景を想像し、一生を一匹の犬と共に過ごすというようなことを夢見ていたのだった。「南極物語」や椋鳩十さんの「動物小説」に強く魅かれていた時期だったのだ。
家から食べものをせっせと運び、竹薮の中で小犬を抱いて夕方おそくまで昼寝(?)をした。わたしが竹林の中で小犬をかこっていることを友達も皆知っていて、すでにそれは「みちひろの犬」として認知されていたので、犬が行方不明になっても誰かが見つけ出してわたしに届けてくれるのだった。
ところが1週間ほど経ったある日、その黒い小犬の持ち主が突然現れた。捨て犬ではなく迷い犬だったのだ。友達の誰かが口をすべらせたにちがいなかったが、村で一・二を争う富権者(金持ち)川原家のじじいは、わたしが迷子犬の面倒をみてきたお礼を言いに、温州みかん10Kgの入ったズタ袋を持って夜中にやって来た。結果、わたしが小犬を隠していたこともすべてバレてしまい、隠し事をしていたことを母に叱られることになった。そして肝心の黒い小犬は翌日にはもう竹薮から連れ去られていたのであった。
いつもならおとなしくあきらめて野山にこもってしまうのだが、その時だけは狂ったように泣きながら懇願した。
「あの犬を飼いたい、飼わせてくれ、川原さん家からもらってくれ〜!」
わたしは生まれて初めて意志をもってダダをこねた。しかしそのダダは聞きいれてもらえず、わたしは次の日からまた新たな捨て小犬探しを始めたのだった。超ドライである。昔は春秋ともなると捨てられた小犬が結構いたものである。
3ヶ月ほど経ったある日、学校から帰ると母がニコニコしながらすり寄って来て言った。遠い親戚のうちに小犬が生まれ、もうすぐ親犬から離してもよさそうだから次の日曜日にもらいに行くというのだ。わたしはもう死んでもいいというぐらいに嬉しかったが、そういう時の気持ちを表すのが特に下手な質なのでただ無意味に畳の上で100回ぐらい前転した。
「血統書付きだってよ〜!」母は実に嬉しそうだった。わたしは「けっとうしょ」は「決闘書」だと思ったので、おそらく・きっと・間違いなく猟犬のような強い犬で、これでやっと「精悍な黒い犬と山川海を一緒に走り回る」という夢が叶うのだなあ、と黒目をぐるぐる回しながら喜んだ。さらに犬を飼うことが急に現実になり気持ちに余裕ができたのか「まあ、色なんか別に黒でなくてもいいんだぜ……」などと止まらない笑いを隠すように小林明風の標準語を使ってみせたりした。お調子者である。
しかしだ、母が鹿児島市内の親戚からわたしたちが住む瀬々串(せせくし)という村に連れ帰ってきたのは「真っ白なスピッツ」の小犬だったのだ。
わたしは運動会の朝に新品の靴と真白な靴下を履かされるのを嫌う程度の照れくささで、そのスピッツの小犬を見た。
当時まだ村には自動車(自動車だぜ!)が一台も無く、村内の交通機関は農耕用の馬車と自転車だった。そしてほとんどの子供たちはパンツ1枚、そして裸足で村内を走りまわっていたのだ。飼犬もまったくの放し飼いで100%雑種、名前もタロウ・ジロウ・クマゴロウ・サイゴウ・タカモリなどだ。犬たちは自由に群れ、そして交尾していた。
そんな村の中をわたしは「ハッピー」という名のキャインキャイン鳴くスピッツの小犬を毎日散歩させなくてはならない、これが恥ずかしい事以外の何であろうことか! 小インテリだった母はそれなりにプライドを満足させている様子だったが、スピッツの血統書付きの特徴である“とがった口”と“ピンと立った耳”が大きくなってもハッピーに出てこないのが多少不満そうではあった。
まあ、そんなこんなで飼い始めたわたしの犬だったのだが、付き合い始めると情は育まれるのだ。わたしは毎日給食を少しずつ残して持ち帰りハッピーにあげた。黒い犬ではなかったけれど山川海を一緒に走った。獰猛そうな大きな犬に襲われた時など、わたしは身を呈して彼を守り自分が4針縫う傷を負った。わたしと彼は、そうして信頼を作っていった。もう黒い犬でなくても、気だけが強いスピッツでもよくなっていった。そして耳の後ろにかすかに黄色味を帯びた毛があることを発見した時、わたしはハッピーと友達になった。血統書なんて糞くらえってなもんだ。
小学3年から4年生になる時、わたしは転校した。隣の中名(なかみょう)という村に移っただけだったが子供にとってはおおごとだ。家が変わる、友達がいない、遊び場が変わる。田舎というのは外から入って来るものに対して非常に警戒心が強いのだ。出そうな釘は出る前に打て、という鉄則があるようで、わたしはすぐに上級生たちになぐられた。悔しかったが体が違う、わたしはハッピーと語った。散歩に連れてゆくと、みかけが恐い犬ではないから4、5歳の小さい子供たちからさえも石を投げられた。そうしてわたしとハッピーの間には連帯感も生まれていったのだ。ハッピーの悩みなども分かるようになり、それらは主に性の悩みのようであった。わたしもその手の話を彼にだけはよくしたものだった。
18歳の誕生日を迎える2ヶ月前に、わたしは東京で1人暮らしを始めてしまったので、それ以降ハッピーとは年に1度、帰省の折りに会うだけの関係になってしまった。
わたしが帰省して家の手前50mまで来ると、ハッピーはヒーウッ、ヒーウッと喉を詰まらせた女のような声で鳴いた。その声を聞いて父母は息子が帰って来たのを知るのであったが、息子が自分たちに「ただいま」とあいさつする前に飼い犬の所へ直行するのが気に入らないらしく、よく「東京へ連れていけば?」と冗談を言われたものである。母などは真剣に「嫉きもち」をやいているように見えた。
そんな状況が3年ほど続いたある日、わたしは夏の狂暴な日差しを浴びながら自宅の手前50mの大きなヤシの木の所まで歩いて来た。……? わたしはハッピーの声がしないことにすぐ気付いた。「散歩にでも行っているのだろうか」口の中に淡い苦味を感じ嫌な予感がした。
普通なら心配でおのずと小走りになるところだろうが、わたしはウスウス感じていたのだ。13歳という犬の年齢を7倍にして人間の歳に換算したりした。そして恐るおそるゆっくりと家の裏口に近づいていった。
床下の一番端の1本の柱に、くくりつけられた鎖がみえた。
「な〜んだ、いたんじゃないか!」わたしはさらに近づき、鎖の先端を見た。
ガビガビになった皮製の赤い小さな首輪があった。
「普通だったらよ〜、鎖も首輪も片付けておくんじゃないか?」
「いつ死んだんだよ、なんで知らせなかったんだよ」
「どんな感じで死んだんだよ、苦しんだのか?」
「遺体はどうしたんだよ、線香のひとつもあげてやったのかよ〜」
わたしには、やさしい父がハッピーを手厚く葬ったであろうことは分かっていたが、悲しくて辛くてやりきれず父に激しくつめ寄った。父はすまなそうに頭を下げたまま、2ヶ月前ハッピーが老衰で眠るように逝ったこと、なきがらはハッピーとわたしがよく遊んだ砂浜に深く深く埋めたことなどを、ボソボソと話した。わたしは感情的になってしまったことを父に詫び、ひとり部屋にこもって少し泣いた。段ボール箱にしまった鎖と首輪をそっと触り「友」と永遠の別れをした。落ち着きをとりもどしたわたしはもう一度居間に戻り、ハッピーのためにも父と飲み直すことにした。
「おやじ〜、鎖と首輪をそのままにしておいたのも、やっぱり全部無くなってると俺が悲しむと思ったからなのか?」
父は、もうその話はやめようや! といったあからさまな表情で言った。
「あ・あ・あ・あれは〜、忘れただけ」
わたしは、人生はあまり深くものごとを考えないでもいいのかもしれない、とそんな気分になった。
犬は今でも飼いたいと思っている。自分の年齢と犬の平均的寿命を考えると、今がラストチャンスかもしれない。しかしもう鎖の先で犬を飼うのは嫌なのだ。鎖の先には人間の都合だけが付いている。
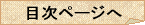
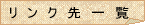
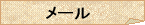 ・
・

