05年9月23日(金)「 クロマメ 」
これといって予定のない今日、ウトウトと8時頃まで惰眠を楽しんでいると耳の奥で娘の声がした。妻の心配そうな声も聞こえた。
「だいじょうぶ、一人で行けると思うよ、地図もあるし」とか言っている。茶トラがどうのこうの、とも聞こえた。わたしはゴソゴソと起き出し「よう!」と言った。
誰かのブログに「土呂の指導農園の中の休憩小屋に捨てられた子猫たちがたくさんいます。だれか里親になってください。25日過ぎには保険所へ連れていかれるのです」とあったらしいのだ。娘はその現場を確かめに行くというのだった。
家を出て独立した娘が猫を飼いたがっているのは知っていた。成人した子供にいちいち意見をするのはやめようといつも思ってはいるが、しかし諸事情を考慮してわたしは一蹴した。
アトリエを持ちたいというから(一応刺繍家を目指している)家を出るのを許したのだ、けっこう大事な時期である。そして何よりも一番の理由は、動物を飼うのにはそれなりの覚悟が必要だからだ。飼い始めたら10年は拘束されるし責任がある。わたし自身、懺悔しなければならない若い頃の軽はずみな失敗も多い。
「猫の頭を撫でたかったらここへ来ればいいじゃないか」
わたしは目の前のウーロンとプーリーをあごで指した。
しかし父親の“やっちゃった者勝ち”的考え方は確実に娘に遺伝したようだった。娘の頭の中には、もう子猫が1000匹ぐらいいる。一人で行かすと確実に2〜3匹連れて帰ってきそうである。で、結局“見張り役”兼“道案内役”でわたしも同行することにした。
秋分の日で道は混んでいたが、わたしと娘はチョイチョイとバイクですり抜けをくり返し目的地の「指導農園」には40分で到着、件の休憩小屋もすぐに発見した。10m四方ほどの畑を市民に貸し出している、よくある市民農園である。そして猫たちは自由気ままにそこで過ごしていた。しかしよくよく見ると、そこに居る猫たちはそれぞれが重いものを背負っているようだった。明らかに尋常、健全ではない。
面倒になって置き去りにされたもの、病気にかかっているもの、毛の抜け落ちたもの、年老いたもの、傷ついて今にも死にそうなもの、そんな猫ばかりだ。唯一、まさに昨夜捨てられたのではないかとおぼしき若猫の活発さが悲しかった。
わたしたちはしばらく近辺を歩いてみた。あちこちに一目でその痕跡とわかるダンボール箱がころがっている。そうなのだ、ここは猫捨てのメッカになっているらしかった。
わたしはまたクドクドと娘を諭していた。来た道を戻るだけだからここから先は別行動にしよう、猫を拾って帰るなら100%自己責任でそうすればいい、わたしはもう関知しない、と言い渡した。そもそもそんなに飼いたいなら、もっと元気でまともな子猫がいくらでもいるじゃないか、ペット病院には里親探しの子猫写真がいくらでも貼ってあるではないか、わたしは口調をきつくした。
通り雨が走ってくる勢いで娘の目に涙が浮かんできた。娘は猫たちがかわいそうだと小学生のように泣きじゃくった。10何年振りに娘の泣き顔を見たような気がした。
いい歳をしたオヤジと20歳の娘が、黙りこくったままバイクの側に立ち尽くしていた。わたしは、やっぱりついて来ない方がよかったのかなあと思った。娘といっしょに走りたいだけでノコノコついて来ただけのような気がした。
「腹が減った!」わたしはぶっきらぼうに言った。
室内で食事をする気になれなくてコンビニで弁当を買い、ベンチのある木陰に入った。赤い彼岸花に混じって所々に白い彼岸花が咲いている。あと何回こうして娘と二人きりになれる時があるだろうか、わたしはそんなことを考えてみたりした。向かいのベンチでどこかのお兄さんがギターを練習している、上の下ぐらいの上手さだ。そして曲はボサノバだった。「イパネマの娘」を聴きながら、わたしは心を少し柔らかくした。
「飯、食い終わったら、もう一度さっきの場所に戻ってみるか」
娘は特に返事をせず、なにごとかを考えながらボサノバを聞いていた。珍しくだいぶこたえているように見えた。
指導農園の休憩小屋に戻るほんの数分間に、わたしは腹を決めていた。わたしは、こうと決めてしまうと“後はどうにでもなれ”タイプなので行動だけは早い。あまりよく分からないが「元気なデカダンス」みたいな感じである。
手当り次第に子猫をいじりまわし、獣医の手付きで目、鼻、耳、尻尾、肛門、性器、腹、骨格を診た。
「この子にしなよ」わたしは上位下達の言い方で黒い子猫を娘に渡した。一方的にも思える決め方だが、そうではない。娘が一番その子猫を気にしているのを、わたしは先刻から無言のうちに承知していた。
その子猫はもう半分死にかけて(少なくとも見る限りでは)いた。ひどい風邪で鼻がつまり、くしゃみをすると粘着質の鼻水が四方に飛んだ。肋骨の辺りに突起があり、もしかするとカラスにでもつつかれて折れているかもしれなかった。グッタリと土の上に寝たまま動かない。気の早い蝿が飛んで来そうだった。そしておそらく、その晩にやってくるであろう台風には耐えられそうには見えなかった。つまり、その時点でもっとも助けを必要としていそうな奴だったわけである。わたしは「だれも他のひとが拾いそうにない猫」ばかりをいつも拾ってしまう。
「急ごう!」とわたしは娘に言った。かかりつけの動物病院へ直行である。娘はリュックからペットキャリアーを取り出した。
「なんだ、やっぱりそんなもの持ってきてたのか?」
「まあね」
娘の顔に笑顔が戻った。その笑顔の根底には大きな責任がなければいけないんだぞ、などと言おうかとも思ったがもうばかばかしいのでやめた。それより一刻も早く病院だ。弱った猫はちょっとのことでショック死するので慎重にバイクを走らせることだけを娘に言い、わたしが先導した。信号で止まるたびに娘はキャリアーの中を覗いているようだった。
医者は「3匹目ですねえ」などと言って笑い、15分程で処置を施した。症状は重いが大丈夫だろうとも言った。¥6500を娘が支払い、わたしたちはバイクのエンジンをかけ帰路についた。さまざまな思いが脳裏を横切り、後方へ飛んで行った。わたしはバックミラーを覗き、娘を見た。
わたしは信号で止まった際に、娘のマンションまでは送らないことを告げ、青と同時に左腕を上げ右折した。直進して行く娘が軽やかに短くクラクションを鳴らした。
夜になって妻の携帯に娘からメールが届いた。
「名前は“クロマメ”にしました」
わたしが黒大豆に凝っていることを知っていて、多少は感謝し、とりあえず義理立てでそんな名前にしたのだろうかなどとほくそえんだりもしたが、次の文章でわたしは見事に裏切られた。
「小さな黒い豆つぶみたいでかわいいよ」
……な〜んだそんなことか、オス猫はすぐに巨大になって部屋中に小便なんぞを撒きちらし“ダミ声のエログロ豆”になるぜチクショウ、とわたしはちょっとひどいことを思った。
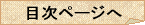
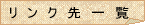
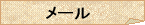 m
m

